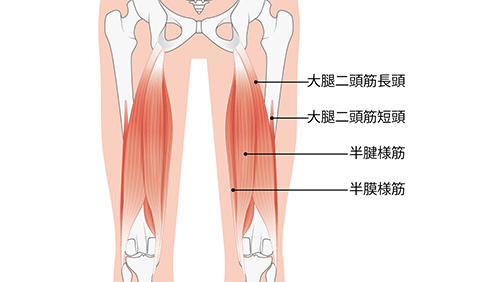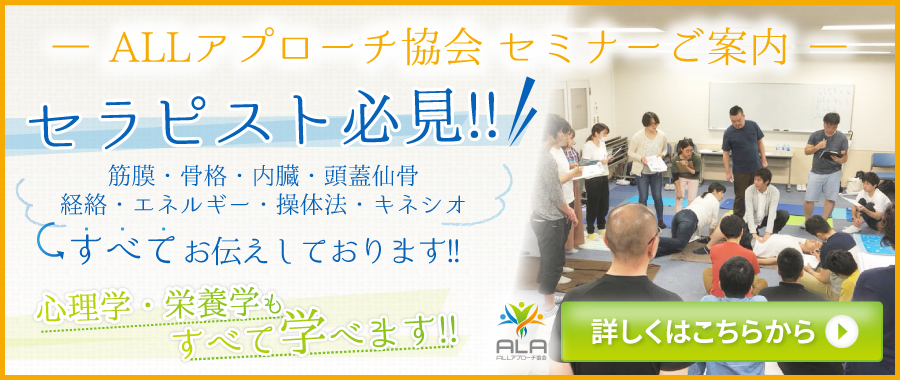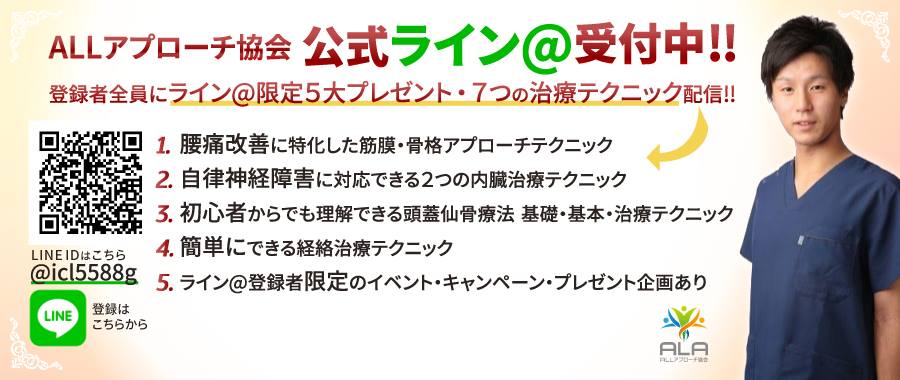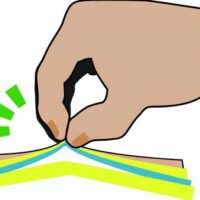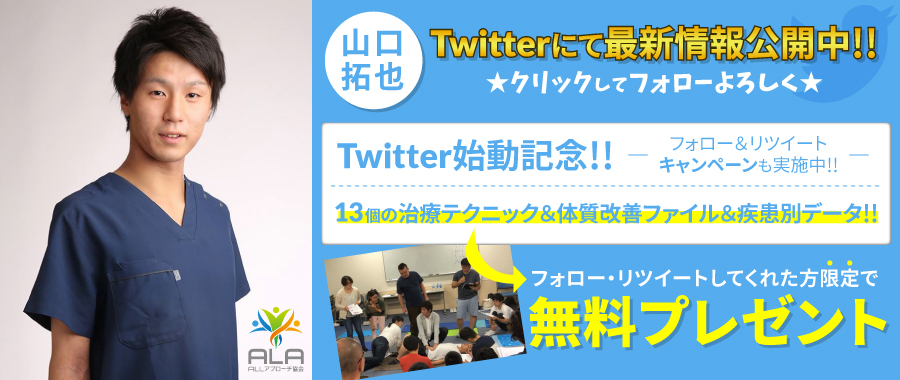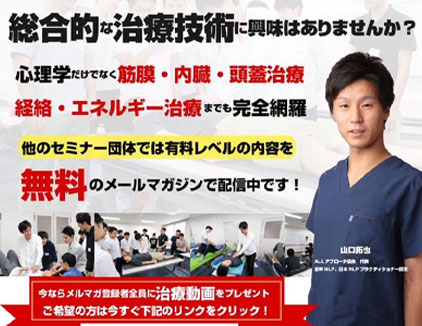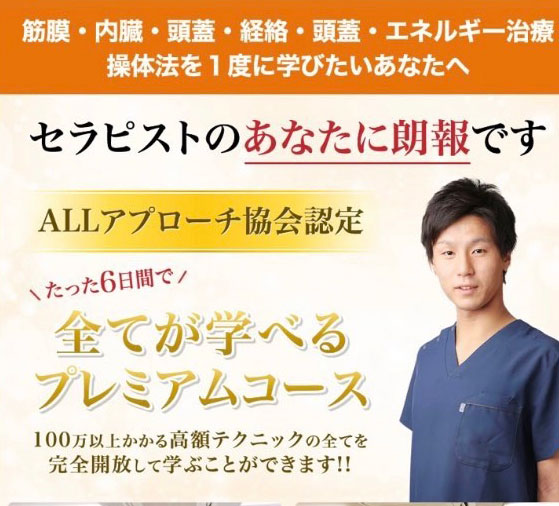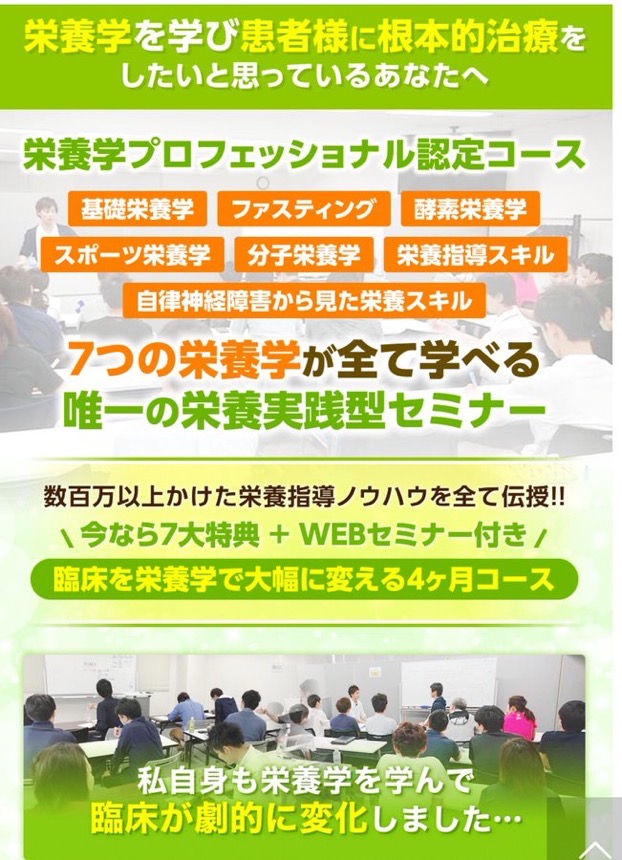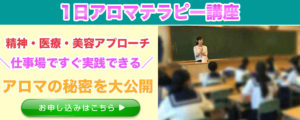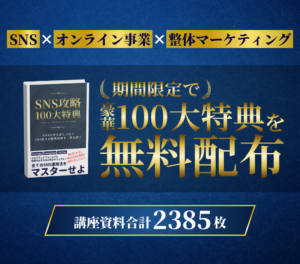皆さん こんにちは
ALLアプローチ協会代表 山口拓也です。
いつもALLアプローチ協会公式ブログをお読み頂き、
ありがとうございます!
今回は、理学療法士、作業療法士、柔道整復師に向けて
「筋膜リリースに必要なジンクパターン」
というテーマでお伝えしていきます。
【ジンクパターンについて!】
治療するうえで、ジンクパターンが何かを知っているかは必須です!
ジンクパターンとは、
アメリカのゴードン・ジンクという方が
筋膜の研究をする中で、体の歪み方には一定のパターンがあることに気付きました。
これを「ジンクパターン」と言います!
ジンクは、代償性パターンと非代償性パターンの2種類があります。
代償性パターンは、交互にねじれますが
非代償性パターン(筋膜)は、変化がなく同じ方向にねじれます。
※8割は代償性のパターン(筋膜)と言われております!交互性とも言われてもいますね。
代償性パターン(筋膜)は、病気やストレスに対して耐性が強いと言われております。
非代償性パターンは、疲れやすく内臓機能が低下し回復も遅い。ストレス耐性も弱いと言われております。
このような、パターンは日々の生活習慣から生じてしまうので非代償性パターン(筋膜)をとる生活をやめる必要があるということですね。
【ジンクパターンを治療に活用?】
このパターンをは4つに分類しており
①頭部と頸部(首) 後頭骨・環椎・軸椎
②頸部(首)と胸郭 胸郭上口
③胸郭と腰部 胸郭下口
④腰部と骨盤 腰仙
①~④部分による身体のねじれパターンを分類し、その人の状態をみるということです。
でも、自分がどんなパターンなのか分かりませんよね。
◆ぜひこれを実践してみて下さい↓
左手が上向き、右手が下向きという身体をねじった形にする
筋膜の方向によりこの形の方が、身体の緊張度が増すのです。
※反対をお試しください。緊張の度合いが減ると思います。
右手が上向き、左手が下向きで緊張が増すなら20%のタイプです。
筋膜調整をするときは、ジンクパターンを意識してリリースをかけましょう。
これを意識することで、リリースする際のベクトルやタッチの深さ、つながりの調整など行うことができます。
本日の記事はこれで以上となります!
インスタやツイッターでも有益な情報配信してますのでぜひフォローお待ちしております。
本日の記事はこれで以上となります!
それでは、また明日!
山口 拓也