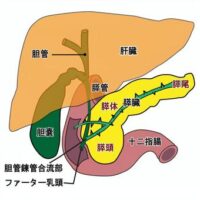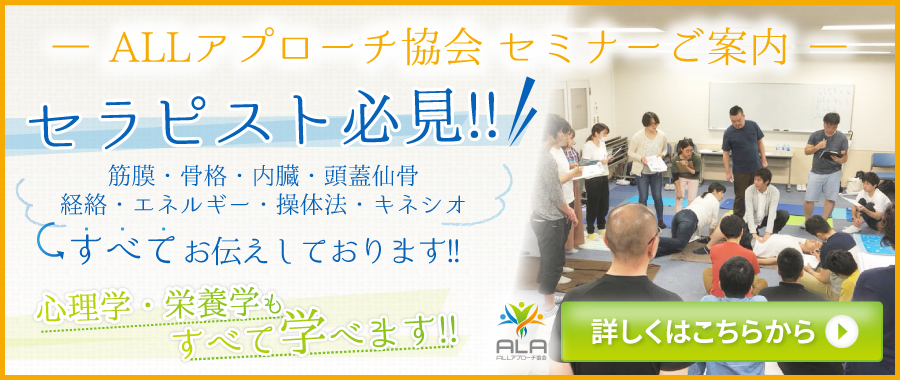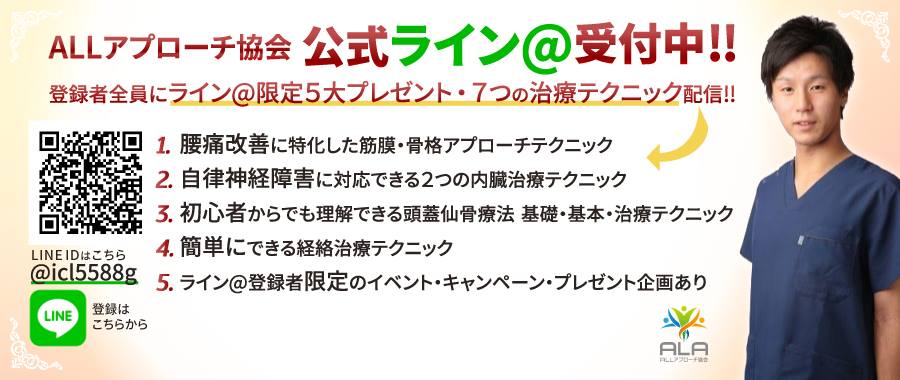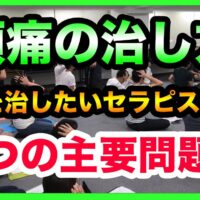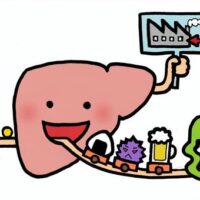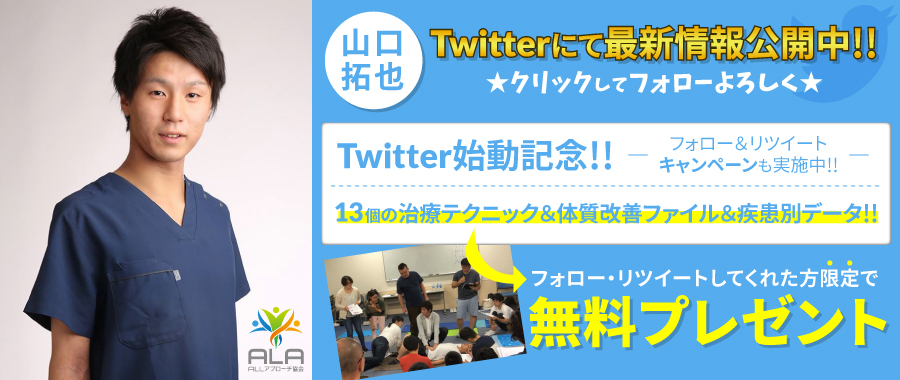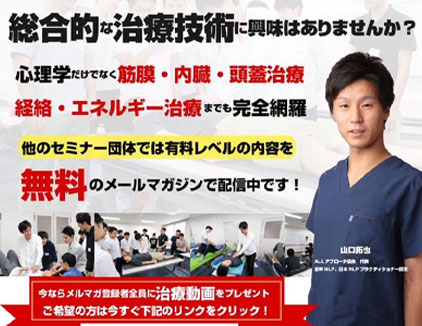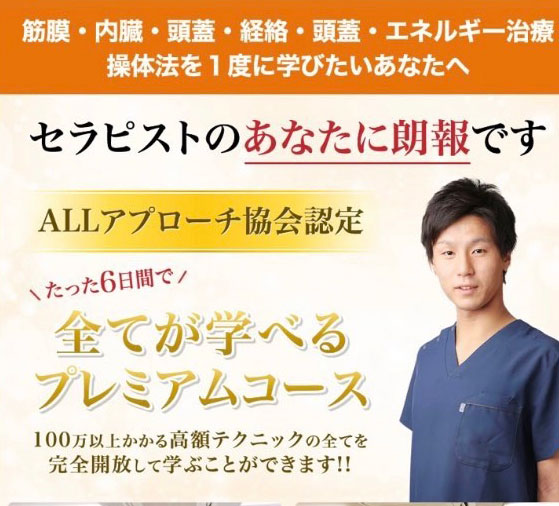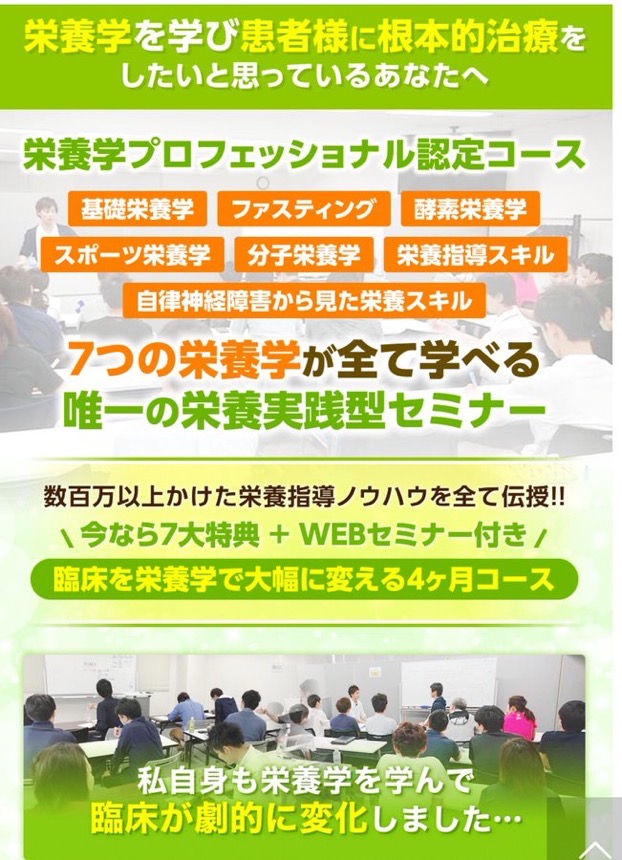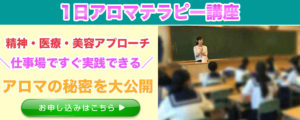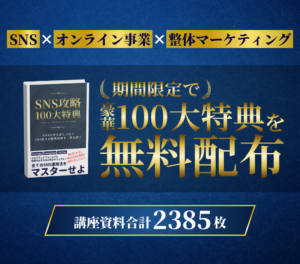おはようございます(^^)
ALLアプローチ協会 ブル と申します。
本日は1~3年目の理学療法士・作業療法士・柔道整復師・整体師など
新人セラピストの先生方に向けて
「頭痛×後頭下筋群×解剖学」
―大後頭神経・椎骨動静脈に着目してー
というテーマについてお伝えしたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
頭痛に悩んでいる患者さんって多いですよね・・・
こういう患者さんは
「肩こり」や「首こり」にも同時に悩んでいることも多いです。
実際に、最近担当した患者さんは肩こりが主訴で頭痛にも悩んでいました。
症状は後ろ頭から痛くなり目の奥が重いよう感じがするとのことで、
夜寝る前に痛み止めを飲んでいたそうです・・・
評価・アプローチしていく中で、特に後頭下筋群へのアプローチによって
頭痛が軽減していきました(^^)
まだ肉体労働をした後などは時折痛むこともあるのですが、
今では痛み止めを飲まずに寝れるようになっています。
本日は「どうして後頭下筋群が頭痛と関係するのか」という事を
解剖学の視点を交えて考えていきたいと思います。
少しでも皆様の臨床のヒントになれば幸いです♪
本日の目次
‣ 後頭下筋の基礎知識
‣ 固有受容器が豊富で硬くなりやすい
‣ 頭痛と大後頭神経 走行と圧迫部位
‣ 頭痛と椎骨動脈
‣ 生活習慣と後頭下筋
‣ まとめ
【後頭下筋群の基礎知識】
後頭下筋群は片側4つ左右合わせて8つの筋群で構成されています。
上位頸椎~後頭骨・上位頸椎に付着している後頭筋の最深層にある筋です。
以下にそれぞれの筋の起始停止を記載しておきますね。
※プロメテウス解剖学コアアトラス第2版を参考にしています。
①大後頭直筋
起始:C2棘突起
停止:後頭骨(下項線の中央1/3)
②小後頭直筋
起始:C1(後結節)
停止:後頭骨(下項線の内側1/3)
③上頭斜筋
起始:C1(横突起)
停止:後頭骨(下項線の中央1/3、大後頭直筋の停止の上方)
④下頭斜筋
起始:C2(棘突起)
停止:C1(横突起)
〇神経支配
後頭下神経(C1の後枝)
【固有受容器が豊富で硬くなりやすい】
後頭下筋(後頭直筋・頭斜筋)は筋紡錘が極めて豊富に分布してい(Cooper and Daniel,1963)
と言われています。
そのため、後頭下筋群の過剰な緊張は、
背筋群の緊張を高めて柔軟な脊柱の運動を阻害します。
また、固有受容器が豊富なので、
身体アライメントの崩れを感知し代償することで
過緊張になりやすいという特徴もあります。
他にも眼球運動に関与しているとも言われています。
ちょっと試してほしいのですが、
後頭下筋群を触診しながら眼を閉じて
眼球を左右に動かす(頭は動かさないで下さい)と
筋がわずかに収縮するのを感じることができませんか??
これはつまり、
眼球運動によって後頭下筋の緊張が変化するということです。
また不安や恐怖などの感情との関連もあり、
情動という側面からも過緊張になりやすい筋です。
大脳辺縁系(情動的原因)と筋緊張
大脳辺縁系は動機と記憶、感情に関する領域が含まれる
不安や恐怖も
感情と筋緊張は関係あり
大脳辺縁系が直接的に支配する後頭下筋群、顎部、肩甲挙筋、骨盤底筋、横隔膜が影響受けやすい
不安恐怖
↓
筋紡錘過敏
↓
上記筋緊張↑
↓
アウターマッスルまで緊張
以上のことから
様々な状況や原因によって硬くなりやすい筋だということがわかります。
ふむふむ、
なるほど後頭下筋群は身体の様々な状況に対応して硬くなりやすい
ということはわかった・・・
でも硬くなるとどうして頭痛になるのかな??
という疑問を解決するヒントとして
後頭下筋群とつながりのある神経・血管をみていきたいと思います♪
【頭痛と大後頭神経 走行と圧迫部位 眼神経との関連】
「頸椎由来の頭痛には大後頭神経が関与している」
という報告があります。
では大後頭神経ってどんな役割を持っているのでしょうか?
以下に簡単に解説してみます。
大後頭神経は第2頸神経の後枝で、
後頭部の知覚を支配しています。
ですので
神経が圧迫伸張されると後頭部に疼痛などを引き起こす可能性があります
この大後頭神経は後頭下筋群の一つである
下頭斜筋を迂回して
キュッと鋭角に走行を変えて後頭部に走行していきます。
この下頭斜筋を迂回して鋭角に走行を変える場所は
外力が集中する場所とも言われてます。
また、
後頭下筋群の極めて近い場所を走行しているので
その緊張は神経に影響を与えてしますことが考えられます。
他にも頭半棘筋や僧帽筋を貫通する部位が絞扼されやすい場所である
と報告されていますのでぜひ参考にしてみて下さいね♪
〇大後頭神経と眼神経の関連
大後頭神経は眼神経(三叉神経の第1枝)ととても近い場所に位置しているため
関連があると言われています(大後頭神経三叉神経複合体)
そのため、
後頭下筋群の過緊張によってこれらの脈管系が圧迫されて生じた
頭痛とあわせて眼精疲労などの目の症状を引き起こすことがあります。
冒頭で紹介した患者さんの目の奥の違和感の症状は
ここからきていたのかもしれませんよね♪
【頭痛と椎骨動静脈】
椎骨動静脈・後頭下神経は後頭下三角内を走行しています。
後頭下三角とは大後頭直筋・上頭斜筋・下頭斜筋によって囲まれた
三角形の部分のことです。
椎骨動脈は頭蓋内(脳へ)へ栄養を送ります。
そのため、後頭下筋群の過緊張によって
これらの椎骨動静脈が圧迫されると
血流障害によって痛み物質が溜まってしまったり、
栄養が滞ることで頭痛などの症状を引き起こす可能性があります。
椎骨動脈と後頭下三角
後頭下三角の近くを椎骨動脈・後頭神経が走行
椎骨動脈見るとすごいカーブでいかにも血流障害起きそう。
【生活習慣と後頭下筋群】
デスクワークが多く、不安や恐怖などのストレスに悩まされる現代人は
特に後頭下筋群が硬くなりやすい傾向にあります。
例えばデスクワーク。
デスクワークでの姿勢は
前腕回内位からの連鎖で胸筋が短縮し猫背となり、
頭頚部前方突出かつ過伸展(ヘッドフォワードポジション)となり
後頭下筋群が短縮位で長時間の作業を行うことになります。
ですので後頭下筋群は硬く短くなりやすいです。
その結果、血管や神経を圧迫絞扼して頭痛や肩こり首コリなどの症状を
引き起こす可能性があります。
また、
後頭下筋群はインナーマッスルとして
安定や固定、軸となる役割をもっています。
後頭下筋群が硬くなるとこれらの機能が発揮できず、
アウターマッスルである僧帽筋や肩甲挙筋が過緊張となり
肩こりや首コリにつながるということもあります。
これらの事からも、予防や再発を防ぐためにもセルフケア指導や
生活習慣指導が必要になります。
【まとめ】
‣後頭下筋は固有受容器が豊富に分布しているため、
役割が多く硬くなりやすい
‣大後頭神経に悪影響を与えて頭痛となるケースがある。
目の奥の違和感とも関連がある。
‣椎骨動静脈の圧迫による血流障害が頭痛の原因になることもある
今回は頭痛×後頭下筋群×解剖学についてお伝えさせて頂きました。
もちろん頭痛の原因はこれだけでなく他にも多くの原因が考えられます。
今回は大後頭神経と椎骨動静脈、後頭下筋群との関係性に
テーマを絞って解説させて頂きました。
頭痛に苦しんでいる患者さんはとても多いです。
今回のブログの内容が少しでも臨床のお役にたつことができれば幸いです♪
本日は以上になります。
最後までブログをご覧頂き、本当にありがとうございました。