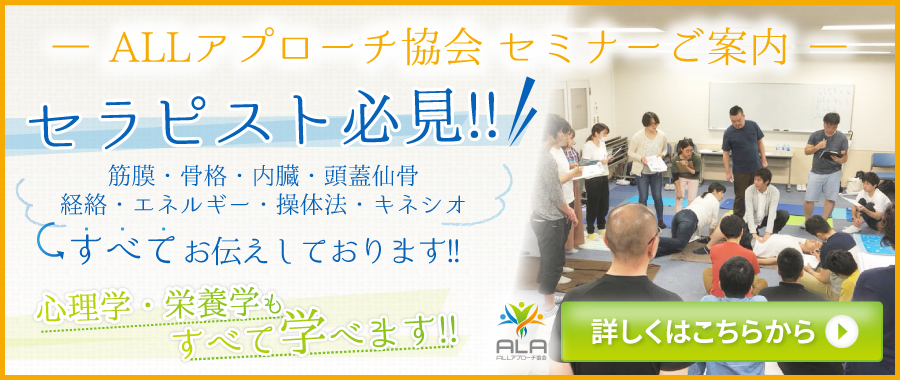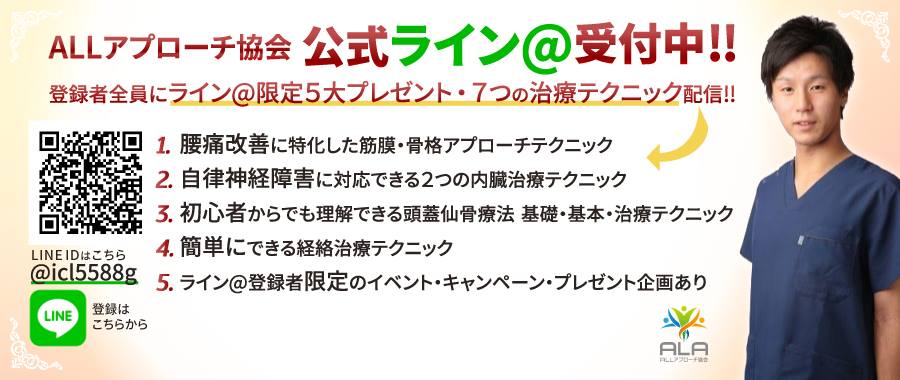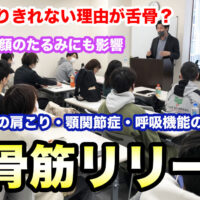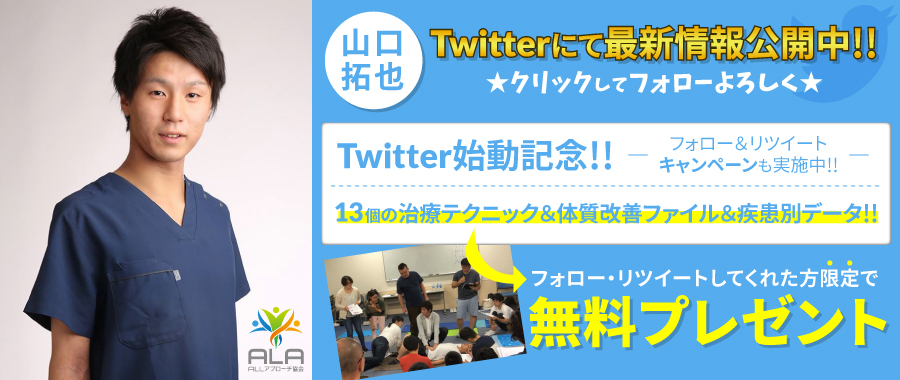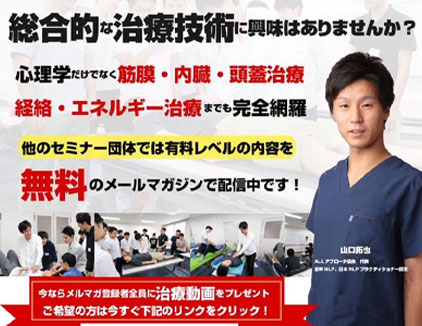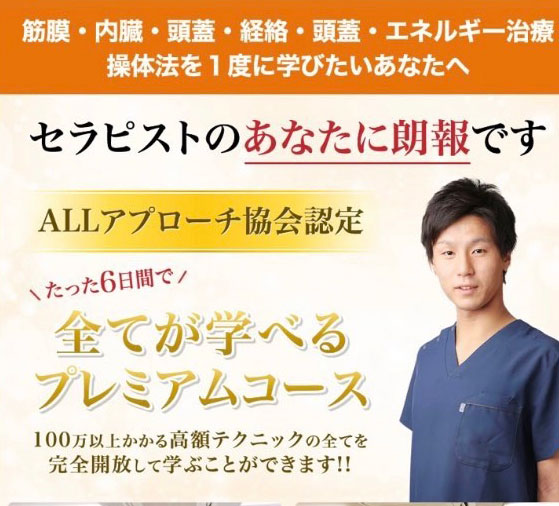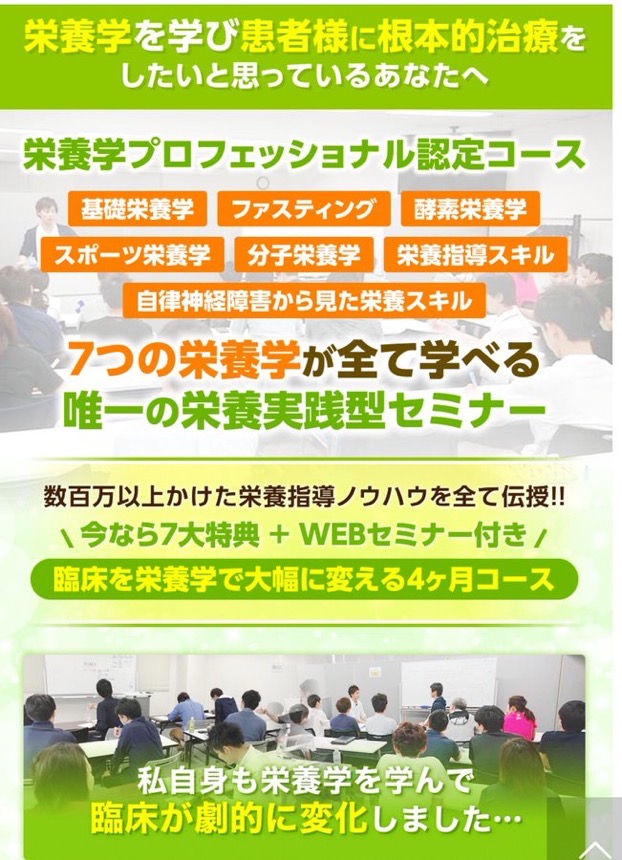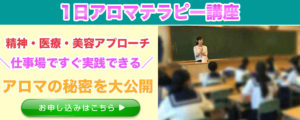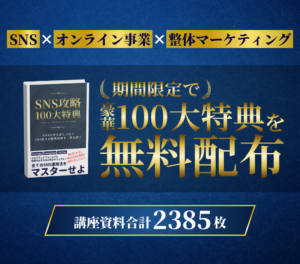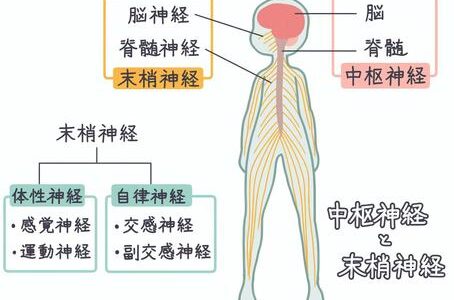こんにちは。
ALLアプローチ協会 触診大好きセラピスト ブル と申します。
本日は1~3年目の理学療法士・作業療法士・柔道整復師・整体師など
新人セラピストの先生方に向けて
「ここで再確認!胸骨の解剖学と触診」
というテーマでお伝えしたいと思います。
もう知っているという方は復習にご活用頂ければ幸いです♪
【胸骨の解剖学的特徴】
胸骨は以下の3つのパートで構成されています。
・胸骨柄
・胸骨体
・剣状突起
〇胸骨の形状と関節
胸骨柄の上縁は頸切痕と呼ばれ、
その両側に鎖骨切痕があり胸鎖関節を形成します。
ここは硬くなりやすい場所です。
胸鎖関節は鎖骨運動の支点なので
硬くなると鎖骨の可動性が低下してしまいます。
その結果、
肩関節可動域低下や肩関節運動時の痛みの原因にもなりうる
重要なポイントです。
胸骨柄と胸骨体の結合部は胸骨角と呼ばれ、
触ってみるとわかるのですが
ボコッと少し突出しています。
この胸骨角はとてもわかりやすいので
同じ高さに位置している第2胸肋関節のランドマークになります。
ちなみにこの第2胸肋関節と胸鎖関節の間に第1胸肋関節が位置していますよ♪
胸骨体には第2~7肋軟骨が関節しています。
第3~5胸肋関節はほぼ等間隔(約1横指幅)で並んでいるのも
触診のポイントになります♪
第6~7胸肋関節は接しているため両者の間隙はほとんどありません。
第7胸肋関節が胸骨体と剣状突起を区別するランドマークになります。
【胸骨に付着する組織】
<筋>
大胸筋
胸横筋(肋骨内部)
腹横筋
横隔膜(剣状突起に付着)
腹直筋(剣状突起に付着)
これらの筋のどれかが硬くなっても
胸骨という中継地点を介して影響し合っていきそうですね♪
そしてここに記載している組織以外にもその影響が波及する可能性があります。
例えば
なんらかの影響で胸骨に付着する組織にトラブルが生じた場合、
それが仮に剣状突起に付着する横隔膜だったとすると、
そのすぐ下方にぶら下がっている肝臓にも影響を与える可能性があります。
また、横隔心膜靭帯を介して心膜へもその影響を与える可能性があります。
ここは胸骨にまつわる様々な組織のつながりを深掘ってみると
面白い発見があると思います♪
当協会のブログや動画にもそのたくさんの情報がありますのでぜひご覧下さいね!
<胸骨と心臓のつながり>
胸骨と心臓は靭帯(胸骨心膜靭帯)でつながっています。
ですので胸骨の硬さが靭帯、心膜と繋がり
胸腔内の硬さを引き起こして呼吸に影響することも考えられます。
他にも心膜からのDFLへの影響(心膜はDFLの一部)なども考えられます。
胸骨は肋骨を介して脊柱とつながっていますので、
胸骨の硬さが脊柱の可動性に影響する事や
その反対も考えられますね(^^)
では次に、触診方法をお伝えしますね♪
【胸骨の触診方法】
被検者の肢位:背臥位
<胸鎖関節の触察>
胸骨柄の上縁(頸切痕)を触り、外側に指を進めながら
鎖骨と胸骨の境界を触察します。
または
鎖骨を触察し、胸骨に向かって指を進めながら
鎖骨と胸骨の境界を触察しても構いません。
〇確認の方法
鎖骨と胸骨の境界に指を当て、
指の半分を鎖骨に、もう半分を胸骨に当てた状態で
鎖骨の挙上と下制を反復してもらいます。
挙上に伴って鎖骨は下方へ滑り、
下制に伴って上方へ滑る様子を触察して確認します。
<第2胸肋関節>
ランドマーク:胸骨角
胸骨柄から尾方にたどると、前方に突出している骨を触察できます。
ここは胸骨柄と胸骨体を結合している部分になります。
この胸骨角から外側へ指を進めると、
第2胸肋関節の裂隙を触診できます。
<第1胸肋関節>
第2肋軟骨と鎖骨との間に位置するのが第1肋軟骨になります。
鎖骨胸骨端のすぐ尾方です。
第1肋軟骨の内側に指を進めると第1胸肋関節の裂劇を触診できます。
<第3~5胸肋関節>
第3~5胸肋関節はほぼ1横指の間隔で並んでいるので、
第2胸肋関節の尾方で第3胸肋関節を触察したら、
そこから約1横指ずつ尾方へ指を移動させて触診していきます。
<剣状突起と第7胸肋関節・第6胸肋関節>
胸郭の下縁を胸骨に向かってたどっていき、
剣状突起と胸骨体の境目の溝を確認します。
この境目から外側に指をすすめると第7胸肋関節が触察できます。
第7胸肋関節のすぐ頭側に第6胸肋関節があります。
ただしこの両関節の間にはほとんど間隙がないので注意が必要です。
以上が胸骨・胸鎖関節・第1~7胸肋関節の触診方法になります。
家族や同僚と試してみて下さいね。
本日は以上になります。
最後までお読み頂き、本当にありがとうございました。