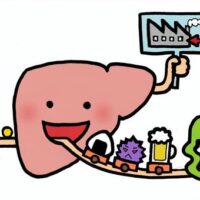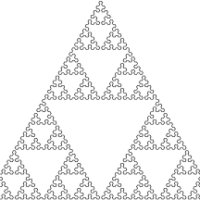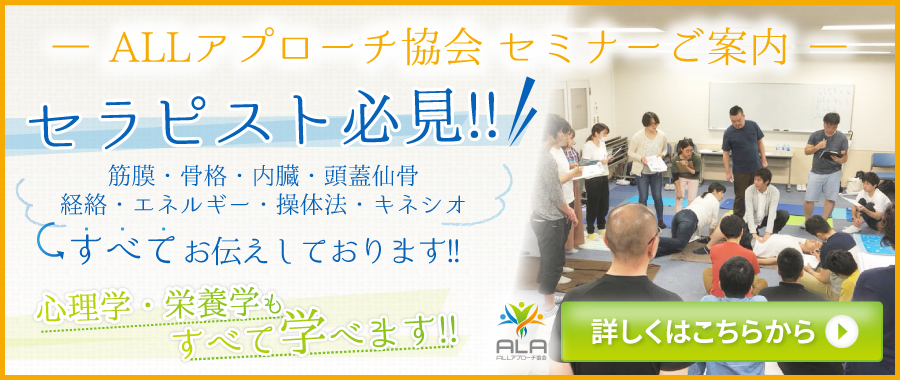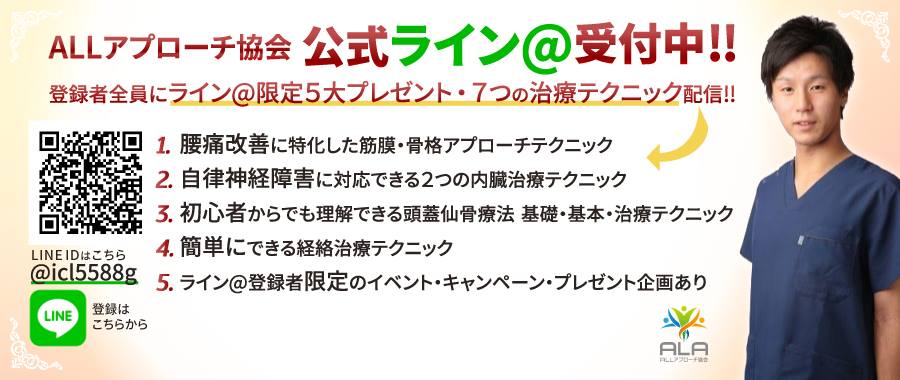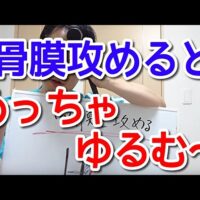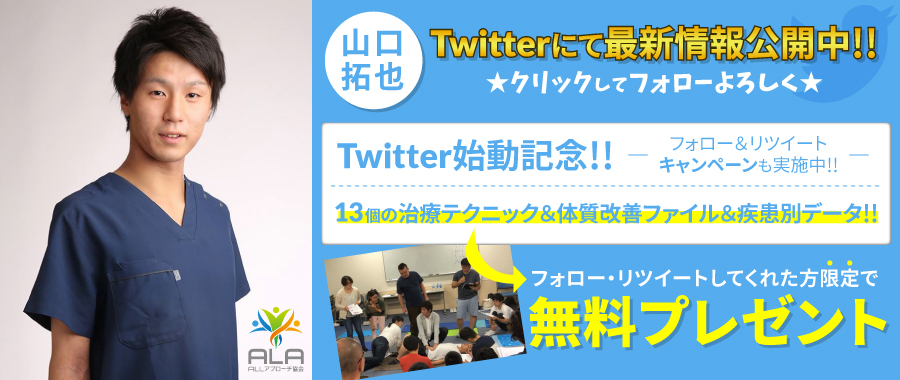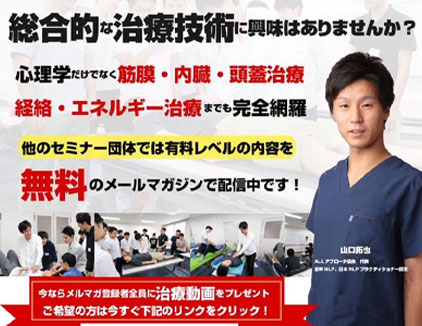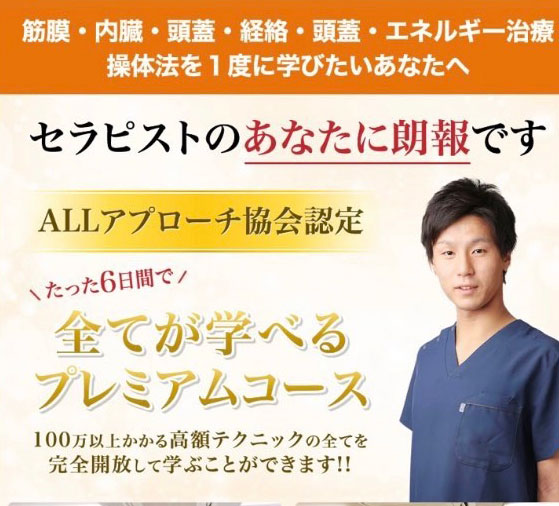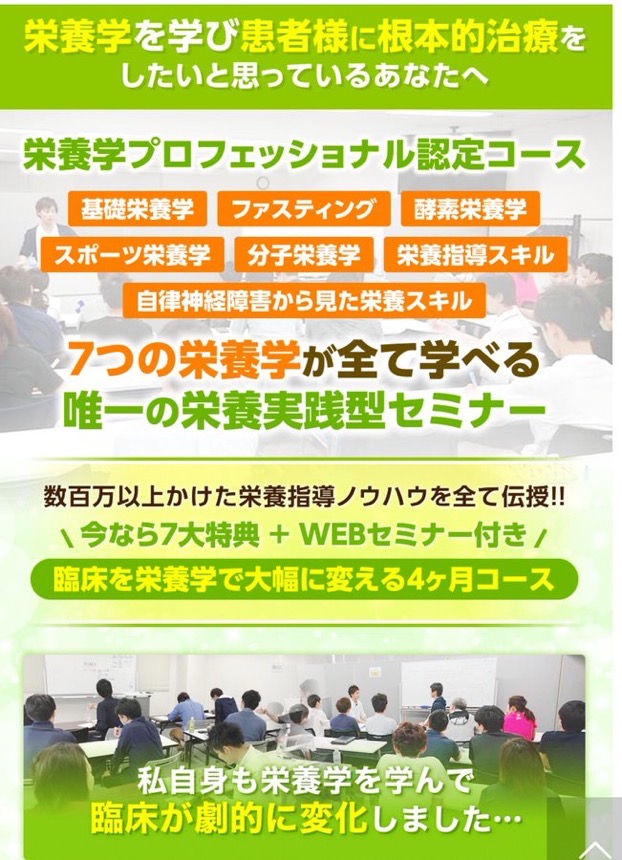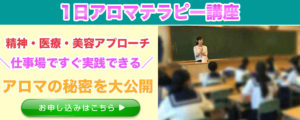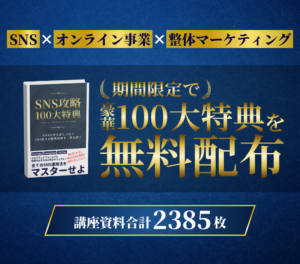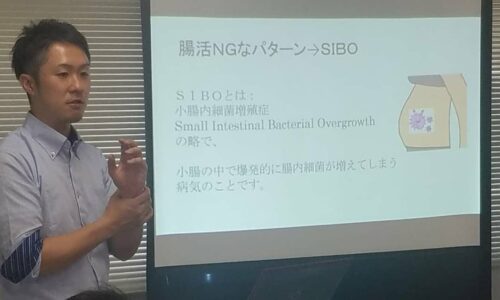いつも大変お世話になっております。
最近、インスタグラムにはまっているALLアプローチ協会 代表 山口拓也です。
いい投稿しているので、是非フォロ-して下さいね。
本日の記事ですが
「筋緊張・筋硬結・筋弛緩の評価〜治療」
について書かせて頂きます。
皆さん
臨床で筋膜調整のアプローチをよくすると思いますが
しっかり筋肉の異常を判断できていますか?
筋弛緩の筋肉をさらに緩めたりしていませんか?
結構そこらへんが曖昧なセラピストさんが多いと思いますので
是非臨床の参考にして下さいね。
【筋緊張って何】
まず、筋緊張について書かせて頂きます。
筋緊張とは、文献によって様々ですが
「筋の伸張に対する受動的抵抗、または筋に備わっている張力である」と言われています。
筋緊張があるからこそ
我々は、姿勢保持が出てきているのであり体温調節(骨格筋のふるえ)もできている。
リハビリの業界でいうと筋トーヌスとも言われます。
この説明で「難しいな」と感じているのであれば
こういう風に認識しておくと良いと思います↓
・他動的な運動(筋の身長)をする際に筋肉の張力によって抵抗を感じるもの
・生体に必要な不随的な筋肉の持続的収縮(体温調節・姿勢反射・伸張反射など)
こんな風に認識しておくと分かりやすいと思います。
身体には、生活や運動で欠かせないのが筋緊張なんですね。
しかしこの筋肉に異常が起きて身体の問題が起こるからこそ
筋緊張を評価しなければいけません。
リハビリの業界だと麻痺の回復段階の指標ともなる評価なので慣れてるとは思います。
【筋緊張が高い・低い】
まず、筋緊張は状況によって
高くなったり低くなったりしなければいけません。
高筋緊張と低筋緊張がありますが、どちらも状況によって変化ができれば正常です。
運動している際は、メインの筋肉は高筋緊張だしリラックスすべき筋肉は低筋緊張となります。
しかし、安静時など意味のないときでも高筋緊張や過度な緊張の場合は異常な筋緊張となります。
もちろん、筋緊張も低すぎると問題になりますから
正常なのか?異常なのか?を判断しなければいけません。
評価の方法としては、安静時で正常な筋緊張なのか?
動作時に過度な緊張はないか?緊張が低すぎないか?
を正常と比べて判断します。
リハビリの学生時代は、筋緊張の評価で
クラスメンバー全員の筋肉の緊張を触って正常がどれくらい緊張なのか評価しませんでしたか?
それだけ、筋緊張の評価は経験値が
必要な評価となります。
拘縮や強直は可動域制限の話なので違いますから注意しましょう。
【異常な筋緊張の種類】
異常な筋緊張の種類はいくつもあります。
■異常な筋緊張
①痙縮(痙性)
痙縮は、脳卒中でよく見られる筋緊張ですね。
リハビリ現場だと、この緊張をよくみると思います。
この筋緊張の問題として「α‐γ連関」が関連します。
この説明すると長くなるし、すぐ忘れると思うので(実際、リハビリ現場から離れすぎて忘れてました笑)
割愛しますね。
まあ、簡単に話すと脳出血などで錐体路系に損傷が起きて
大脳皮質が抑制できずに錐体路系が過剰に活動して
運動ニューロンが脊髄レベルで興奮して(α‐γ連関)筋緊張が高くなってしまいます。
脳の錐体路系から引き起こされる異常なため
自然治癒力で治るのを待ってリハビリするのが一般的となってますね。
治りにくい筋緊張なので整体で痙縮パターン来ると
「大変だなぁ」「自然治癒力あげなきゃ」と毎回思います笑笑
やりがいは非常にあるんですけどね。
②固縮(歯車様)
パーキンソン病などで見られる筋緊張ですね。
正直、リハビリ現場抜けてから
一度も固縮の患者さんを見なくなってしまったのですが、厄介な筋緊張です。
痙縮は、錐体路に問題がありますが
錐体外路がやられて起こるのが固縮となります。
錐体外路系の問題は、中脳の黒質から線条体へドーパミン作動性ニューロンの問題で引き起こされるのが影響です。
そして歯車様の筋緊張となります。
③筋スパズム(筋攣縮)
理学療法の分野では「痛みなどに起因する局所的で持続的な筋緊張の亢進状態」を指すことが多いと言われています。
他にも様々な原因があると言われており
痛み原因
筋・筋膜原因
骨・関節・腱・靭帯の病理原因
末梢神経の刺激・損傷・変性過程原因
これらの複合
上記の問題には、すべて局所の循環障害が引き起こされて脊髄反射から引き起こされるので
循環障害を治すのが一番の近道と言ってもいいかもしれませんね。
④筋硬結
一般的に言われている「凝り」の代表的なものが「筋硬結」です。
特徴として、筋繊維の一部に限局した部分が収縮した状態であり筋の硬さと圧迫したときの痛みがあります。
筋硬結は、押すと圧痛があることから
圧痛点とも言われますね。
一過性の過大な負荷がかかりアクチンとミオシンが癒着し血流障害やエネルギー障害から癒着が持続したものが筋硬結です。
簡単に言えば、筋の一部分が癒着しているってことですよ!
筋膜リリースでは、この硬結をしっかりアプローチすることが重要です。
⑤低緊張(正常とは逸脱した安静時や動作時など)
低緊張は、遺伝的な要素や麻痺の初期段階などがイメージしやすいと思います。
肩の脱臼などもローテーターカフの損傷などの低緊張からも引き起こされます。
低緊張の場合は、筋収縮を入れるアプローチをして緊張を入れる様にしておきましょう。
筋緊張をしっかり評価しないと正確なアプローチができませんので
しっかりアプローチしておきましょう!
最後まで見ていただき誠に有難うございました。
ALLアプローチ協会 代表 山口拓也