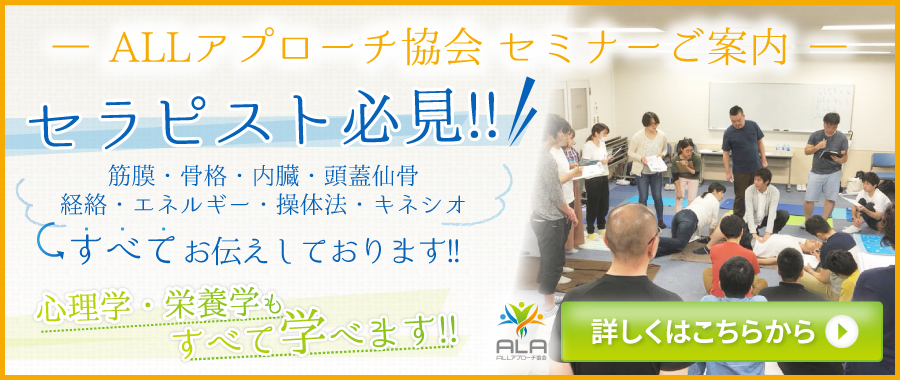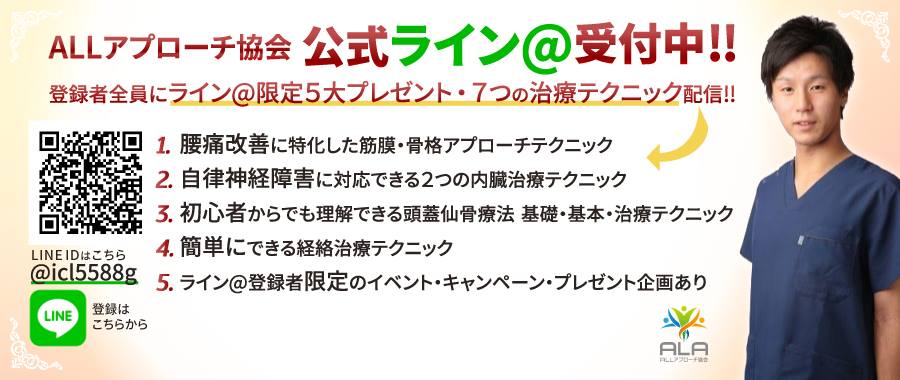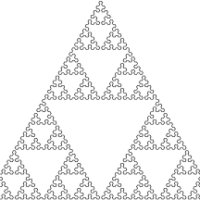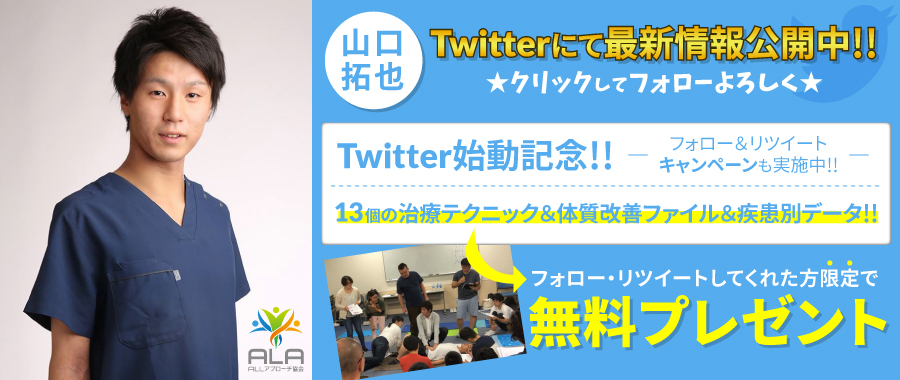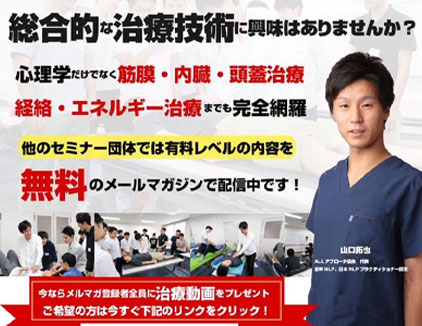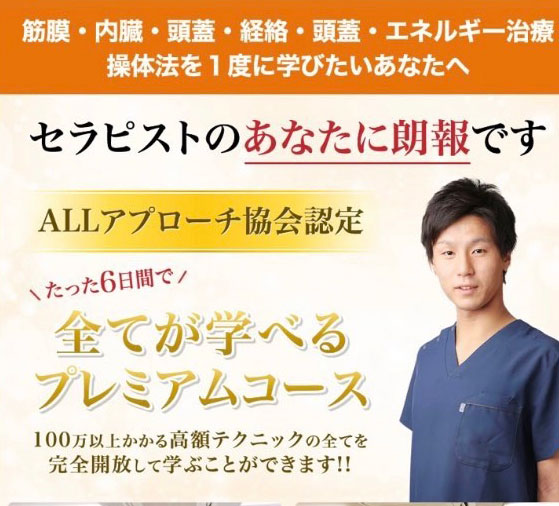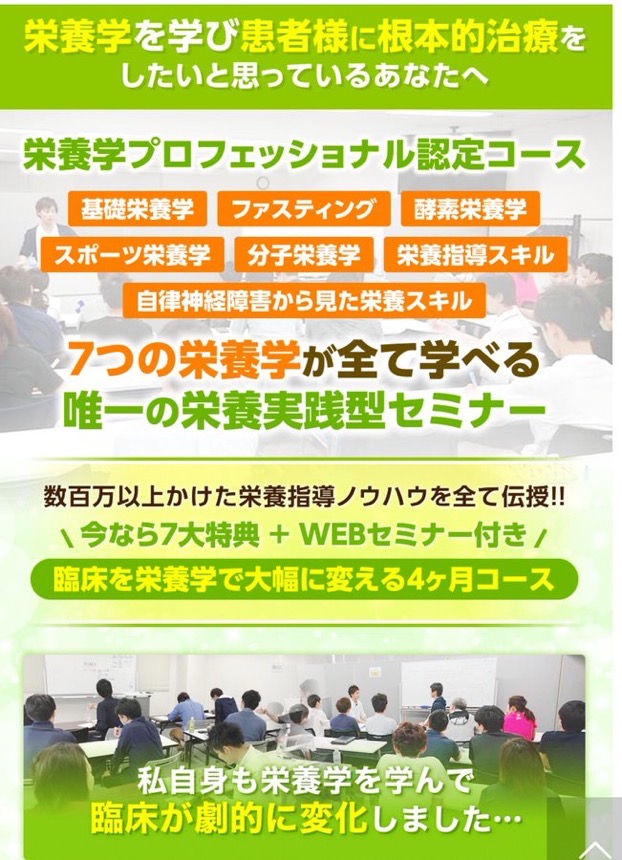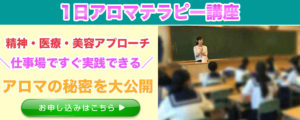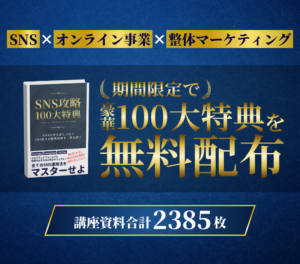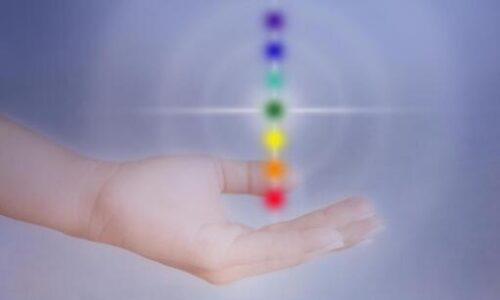ALLアプローチ協会 触診大好きセラピスト ブル と申します。
本日は1~3年目の理学療法士・作業療法士・柔道整復師・整体師など
新人セラピストの先生方や学生の方々に向けて
「ここで再確認!鎖骨・胸鎖関節・肩鎖関節の解剖学と触診」
というテーマでお伝えしたいと思います。
もう知っているという方は復習にご活用頂ければ幸いです♪
肩関節の動きを評価する時には
肩甲上腕関節・肩甲胸郭関節の動きに注目する事が多いと思います。
もちろんとても重要な関節です!
ただ他にも肩関節の動きに関連する関節や骨があります。
それが鎖骨・胸鎖関節・肩鎖関節です♪
この関節や鎖骨の動きを理解し、
しっかり触れるようになる事がこのブログの目的になります。
もう知ってるよ!という方は復習としてご活用頂ければ幸いです♪
【鎖骨・胸鎖関節・肩鎖関節ってどんな形?】
〇鎖骨の形:
鎖骨を上から見ると特徴的でS字上に彎曲しています。
内側の2/3は前方凸、外側1/3は後方凸となっています。
〇胸鎖関節:
鎖骨と胸骨柄の鎖骨切痕で形成される関節です。
この胸鎖関節は鎖骨運動の支点として働いています。
動きは挙上・下制・屈曲・伸展があります。
〇肩鎖関節:
鎖骨と肩峰で形成される関節です。
この肩鎖関節は肩甲骨運動の支点として働いています。
肩鎖関節の可動性は4~8°程度だと言われています。
わずかな動きだと感じるかもしれませんが、
この動きが減少している事で肩挙上痛を引き起こすこともありますので、
侮れません・・・
以上のことからも、
胸鎖関節と肩鎖関節は肩甲骨を適切に動かすために
連動して働いていると言えると思います。
実際に上肢挙上時の肩甲骨上方回旋をみていくと、
肩鎖関節における肩甲骨の上方回旋と、
胸鎖関節における鎖骨の挙上によって行われています。
つまり、肩鎖関節と胸鎖関節の可動性が低下してしまうと、
肩甲骨や鎖骨の動きが低下し、
肩の可動域制限や肩挙上時の痛みにつながってしまいます。
ではその制限因子となりうる筋は
どのようなものがあるのか気になりますよね!
(もちろん靭帯なども制限因子になりますが)
次に鎖骨に付着する筋をみていきたいと思います。
【どんな筋が鎖骨に付着しているの?】
鎖骨前方凸の部分には大胸筋鎖骨部
鎖骨後方凸の部分には三角筋前部線維・僧帽筋上部線維が付着しています。
鎖骨の内側1/3の上縁と前面には胸鎖乳突筋・鎖骨を下制させる鎖骨下筋も外せない重要な筋です。
これらの筋が硬くなると鎖骨の動きを阻害し(肩鎖関節・胸鎖関節)
結果として、肩の可動域制限や痛みを引き起こす可能性があります。
ここでは筋と骨の形状など触診に必要な知識にフォーカスして
鎖骨・胸鎖関節・肩鎖関節をみてきました。
他にも鎖骨と関わるポイントとして
リンパ系・血管神経との関係も重要です。
例えば鎖骨の動きが制限されることで
リンパの流れが悪くなり浮腫みや腫れ、冷え性、疲れやすさ、
首こり、肩こりなどに影響する可能性があったり。
脈管系との関連では腕神経叢や鎖骨下動静脈との関係から
手の痺れにも関与したり、
肩こり、腰痛の原因になることもあります。
これらのリンパや血管・神経と鎖骨の関係については
当協会の公式ブログの記事が参考になるかと思いますのでぜひご覧ください。
では次に、触診方法をお伝えしますね♪
【触診方法】
被検者の肢位:背臥位
〇鎖骨の触診
鎖骨の触診はとてもわかりやすいです。
水平面上でS字になっている骨の形状をイメージしながら
触診していくことがポイントです。
鎖骨の前縁や後縁を指でたどりながら触察します。
鎖骨自体を指で掴んでもOKです。
外側にいくと肩鎖関節があり、内側へたどると胸鎖関節があります。
〇肩鎖関節の触診
鎖骨の前縁を肩峰の方にたどっていくと
肩鎖関節のくぼみのような感触のある関節裂隙が確認できるかと思います。
※わかりずらいという方のための別法
鎖骨の後縁を外側にたどってもらうと
鎖骨と肩甲棘が交わる場所に行きつくかと思います。
その場所が肩鎖関節です。
そこから鎖骨の前縁に指をたどっていくと
肩鎖関節の前方部の関節裂隙が確認できるかと思います。
肩鎖関節の確認方法
肩峰を指でつまんで固定します。
もう片方の手の手掌を鎖骨後縁に当てて
ゆっくりと愛護的に前方に押していくと
肩峰に対して鎖骨が動くのを確認します。
ちなみに
これは可動性の評価にもなりますし、
関節モビライゼーションのアプローチにもなります(^^)
〇胸鎖関節
胸骨の上縁(頸切痕)を触察します。
そこから鎖骨に向かって指をたどると、胸鎖関節の関節裂隙を触察できます。
この時、胸骨の鎖骨切痕と鎖骨との位置関係がイメージできていると
触診がしやすくなりますよ♪
◆確認の方法
関節裂隙に指を当てた状態で、
鎖骨の挙上と下制運動を行ってもらいます。
そうすると、挙上に伴って鎖骨の内側端が下方に滑るのを感じます。
また、下制運動では鎖骨の内側端が上方に滑る様子を感じるかと思います。
以上が触診方法になります(^^)
家族や同僚と試してみて下さいね♪
本日は以上になります。
最後までお読み頂き、本当にありがとうございましたm(__)m