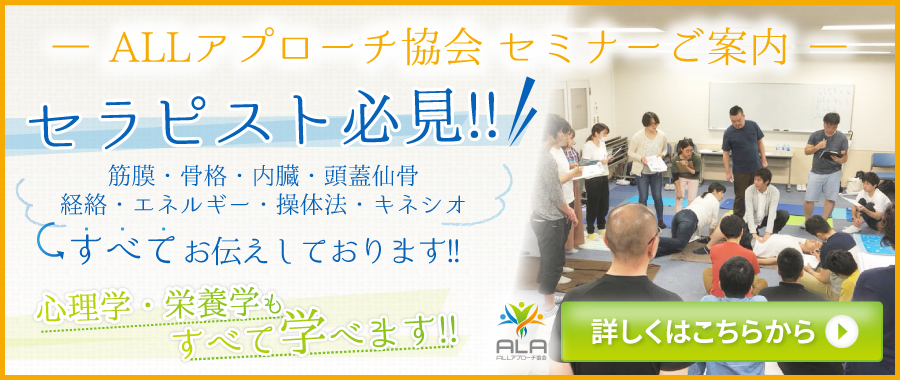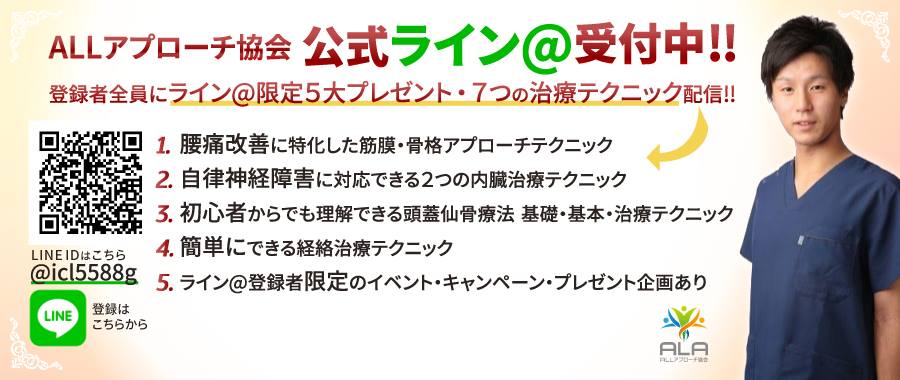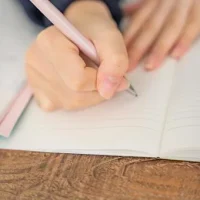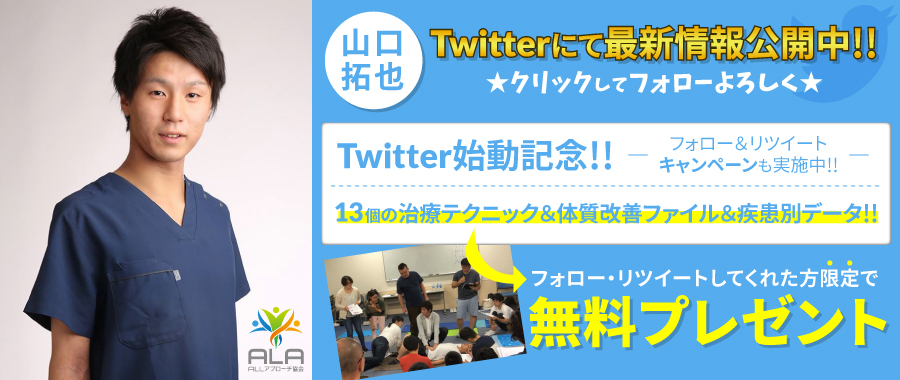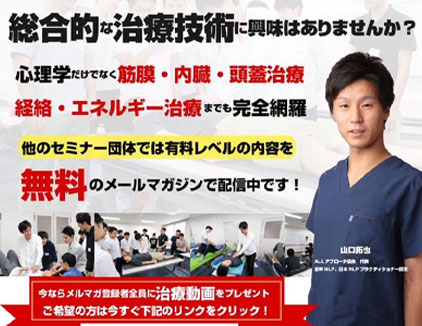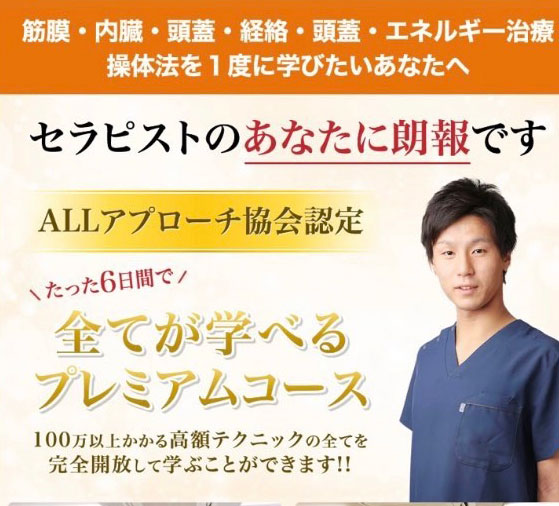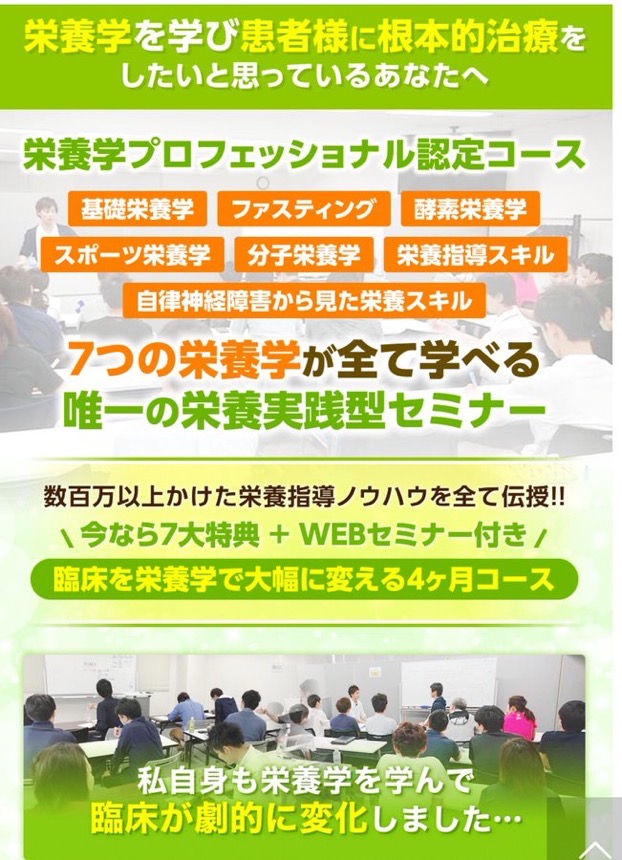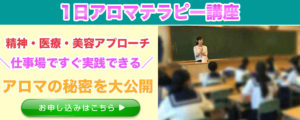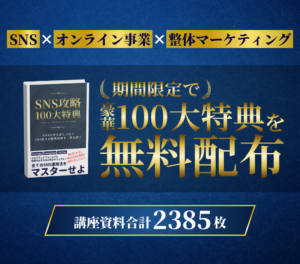おはようございます(^^)
ALLアプローチ協会 ブル と申します。
本日は1~3年目の理学療法士・作業療法士・柔道整復師・整体師など
新人セラピストの先生方に向けて
「足裏のしびれ 屈筋支帯×解剖学×リリース」
というテーマについてお伝えしたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
足裏のしびれを訴える患者様って多いですよね・・・
患者さんの話を聞くと
「もうこれは付き合っていくしかないのよねぇ」
と半分諦めている方も多くいらっしゃいます。
殿部・大腿後面・ふくらはぎとみたけどなかなか改善しない
という事もあるのではないでしょうか・・・
私も思うような結果が出ずに悔しい思いをすることがあります。
そんな中、屈筋支帯へのアプローチで足底のしびれが改善したことがありましたので
本日は屈筋支帯の解剖学とリリース方法についてまとめてみました。
少しでも臨床のヒントになれば幸いですm(__)m
(本日の目次)
① 屈筋支帯とは?
② 屈筋支帯の深層を走行する筋・血管・神経
③ 足底の感覚を司る神経と圧迫絞扼
④ 屈筋支帯リリース
【屈筋支帯とは】
屈筋支帯とは:内果と踵骨にまたがる膜状の軟部組織で
下腿筋膜が厚くなったものといわれています。
この屈筋支帯と足根骨で足根管を構成しています。
ちなみにこの足根管は狭いトンネルのような構造をしていて、
この中を(屈筋支帯の深層を)血管・神経・腱が通過しています。
この屈筋支帯周囲の軟部組織の癒着や滑走性・伸張性の低下が生じた結果、
足底の痺れが生じていることがあります。
では屈筋支帯の深層を走行する筋・血管・神経をみていきたいと思います。
【屈筋支帯の深層を走行する筋・血管・神経】
屈筋支帯の深層を通るものは
‣後脛骨筋腱
‣長趾屈筋腱
‣後脛骨動静脈
‣脛骨神経
‣長母趾屈筋腱
となっています。
これらの組織は足関節で急カーブを描いて足底へ走行していたり、
内果や載距突起を滑車として足底へと走行しているという特徴があるため、
摩擦などストレスのかかりやすい場所とも言えます。
【足底の感覚を司る神経と圧迫】
脛骨神経は3つに分岐し足底を走行しています。
① 内側足底神経
② 外側足底神経
③ 内側踵骨枝
これらの神経は、
足底の知覚支配と足底部の筋肉の運動支配を持っています。
ですので、屈筋支帯周囲で神経の圧迫障害が起こると、
それぞれの神経支配領域に関係する部位、
または3つの神経が支配する領域すべて(踵骨内側から足底にかけて)の知覚異常が生じる可能性があります。
血管の圧迫による影響も重要です。
足根管の狭窄によって後脛骨動静脈が影響を受けた場合は
血流障害によって足のむくみや足底の知覚異常が現れる可能性があります。
屈筋支帯周囲の滑走不全によってこれらの神経や血管に
影響及ぼしていることも考えられますので
ぜひ評価・アプローチして頂けたらと思います。
【評価】
‣足裏の感覚障害の有無
‣屈筋支帯の圧痛
‣dorsiflexion-eversion test(ドルジフレクションエバーションテスト)
ドルジフレクションエバーションテストは足根管症候群の評価になりますが、
方法は足趾伸展+背屈+足部外反を他動的に行い、この状態を5〜10秒保持します。
この動きで症状が出る場合は
足根管が狭小して神経が圧迫を受けている可能性があります。
【屈筋支帯周囲のアプローチ】
屈筋支帯周囲の軟部組織の癒着や滑走性に対するアプローチ
を2つ紹介させて頂きます。
内果と踵を結んだ線の中点を押圧(屈筋支帯を押圧)した状態で
足関節底背屈運動を自動他動運動で行います。
もう一つは,片手で屈筋支帯に手を当て、
もう一方の手で舟状骨粗面(後脛骨筋の停止部付近)や
舟状骨下面(長母趾屈筋と長趾屈筋の交叉する足底交叉部)を押圧して
振動刺激を入れることで屈筋支帯周囲のリリースを行う方法などもあります。
よろしければ試してみて下さいね♪
【注意点】
しびれの症状を引き起こす原因は他にも数多くあります。
例えば,糖尿病による神経症状との鑑別も必要です。
糖尿病のしびれの場合は両方の手や足にしびれが出やすいです。
よく言われていますが
手袋、靴下を着用している部分にシビレが出るという特徴がありますね。
ガングリオンによる血管神経の圧迫や偏平足や回内足による屈筋支帯の伸張が
によってしびれが生じる事も考えられます。
他にも腰痛疾患(腰椎ヘルニア・腰椎すべり症など)や
ギランバレー症候群、閉塞性動脈硬化症などでも痺れが生じる事がありますので
問診や評価で上記のような情報があった場合は医療機関への受診を勧める必要もあります。
偏平足や回内足が原因であれば運動療法やインソール使用なども必要になるかもしれませんね。
今回は足裏のしびれ 屈筋支帯×解剖学×リリースについてお伝えさせて頂きました。
本日は以上になります。
最後までブログをご覧頂き、本当にありがとうございましたm(__)m